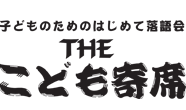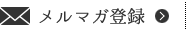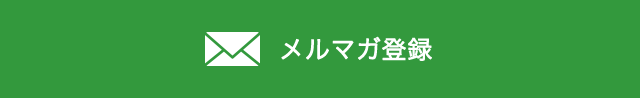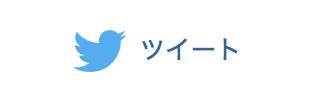公演レポートReport
-
2018.08.02
7.31 夏休み体験付き落語会in越谷

越谷の学童保育施設で昨年から夏休みに開催しています、たっぷり落語体験がついた落語会。1年生から4,5年生まで約40名の学童児童さんにむけ、実際に高座に上がって所作や小話などの落語の第一歩を体験してもらうべく、お迎えしたのは三笑亭可風師匠。最初にいろいろな小話を披露し、その後、数人が実際に高座の座布団の上でトライ。中には自分で考えたネタを披露する子もあらわれるなど、子どもたちのチャレンジ精神と落語をへの関心の高さに脱帽。大変の後に披露した噺は「まんじゅうこわい」。子どもたちの中には絵本等で知っていた子もいたようで、かなりの盛り上がりでした。
こうして子どもたちの日常の中に落語が溶け込んでいく時間がちょっとでもあることが私たちの願い。楽しいことも、辛いことも、最後は笑って生きていくのが、救いになったりすることもあるはず。これからも落語、よろしくお願いしますー。
カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.08.01
7月29日 いろは寄席 vol.3 無事終了


ただ落語を聞くだけじゃなく、高座の上に上がって、小話や所作を実際に披露してみるという、体験付きの落語会「いろは寄席」。約80名ほどのお客様に集まっていただき、春風亭三朝師匠の落語解説と落語を聞いていただきました。
小話の体験に名乗り出たのは3名。三朝師匠の隣で、その場で教わった小話をちょっとしたフリをつけて、きちんと座布団の上でやってみる子どもたちの姿は自分の子どもでなくても、かわいらしく微笑ましいものでした。
所作の体験は4名。蕎麦を食べたり、手紙を書いたりなど、その場限りで見て覚えたわりにはみんな上出来で、会場から自然と拍手が起こりました。
最後の落語は「唖(おし)の釣り」。ちょっとしたハプニングで口をきくことができなくなった七兵衛さんが、何とかジェスチャーだけで意思を伝えようとする仕草が本当におもしろく、子どもたちの中にはお腹を抱えて笑っている子もいたほど。素敵な夏休みの思い出になったことと思います。
カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.07.28
みんなの落語会 春日部&海老名&平塚 7月
 古今亭駒次
古今亭駒次
 三遊亭わん丈
三遊亭わん丈
 三遊亭好の助
三遊亭好の助
 鈴々舎馬るこ
鈴々舎馬るこららぽーと各店(数多くある中のほんの3店舗なのですが)で開催されている、誰でも無料で落語が楽しめる「みんなの落語会」。その中でも、春日部のこの会はとても人気が高く、いつも使用していたコミュニティルームでは入りきれなくなったために、今月よりお隣のユナイテッドシネマの1室(220名収容)を借りての「シネマ落語」となった。出演は古今亭駒次さん。やはり聞く耳がある自然に笑いとかけ声がかかるお客様の前では、いつもの落語も何割増しか面白く聞こえるのは気のせいでないはず。
落語というのは、お客様と落語家で生み出す「気」や「間」によって、面白くもそうでなくもなる生の芸能なんだと思う。春日部の落語は本当におもしろい。それが相乗効果となって人を呼んでいる。ららぽーと海老名も大盛況。先月より毎月第四土曜日開催だったのに加えて、第四水曜日も加わっての月2回の公演となった。これでどちらも盛況というのだから、素晴らしい。今月は25日に三遊亭わん丈さん。29日が三遊亭好の助さん。こちらは60名ほどでいっぱいになる会場がいずれも満席。好の助さんにいたっては札止め。もう座る席がありませんでした。ららぽーと海老名にいくと、いい落語が聞ける、いいよね~楽しみなんだよね、という声がもっともっと広がりますように。
ららぽーと平塚は今年5月からのレギュラー公演となった場所。こちらもよくお客様がお入りになる。それもそのはず。館内にはわかりやすくポスターが掲示されており、呼び込みも万全。しかも私も気合いを入れて、選りすぐりの真打ちの師匠たちに出演頂いている。今回は鈴々舎馬るこ師匠。先月は春風亭百栄師匠。いずれもシブラクで聞いたら映画のチケット代をはるかに超える入場料となる落語家。何とも贅沢の極み。落語を見て、ららぽーとと平塚の町を散策したら、ちょっとしたプチトリップです。
こちらは毎月第三水曜日。ぜひご来場ください。カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.07.02
6月30日 こども寄席 in浦安
 三笑亭夢丸
三笑亭夢丸
 マスター
マスター浦安社会福祉協議会の事業である、子育てファミリーサポート。そのPRイベントとして、こども寄席にお声がかかり、出張公演してまいりました。
出演者は落語が三笑亭夢丸師匠、色物にはジャグリングのマスターさん。いずれも初めて落語を聞く、初めてジャグリングを見るという方にはもってこい!の間違いのない方々。どんなに小さな子でも夢丸師匠の落語解説ならとてもわかりやすくて、ニコニコと聞いていられるのだからさすがです。後半の落語一席は、初心者のための絵付き落語を披露。紙芝居で絵を見せながらの一席「鷺取り」は、大人でも子どもでも楽しめる、コミカルな演目。子どもたちにも笑いが絶えず、素晴らしい一席となりました。
マスターさんは常にストリートパフォーマンスでお客様と対話しながら演技を披露していることもあって、とにかく子どもたちの心をつかむのが早い!しかも、フレンドリーでコミカルなステージの雰囲気なのに、やっていることのレベルの高さがスゴイ! 終わったときには、大人も子どもも大喝采となり、彼のステージがいかに素晴らしいものであったかを物語っていました。
カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.06.18
6月16日 まつもと大歌舞伎2018関連公演 こども寄席 無事終了
こども寄席は年に何回か大きな出張公演に全国に伺うのですが、今年の第一弾は信州・松本。しかも「まつもと大歌舞伎2018」という、松本市をあげてのビッグイベントの関連公演としてお声かけいただいての開催となりました。とにかく、松本駅に降りてから、街は「まつもと大歌舞伎2018」の旗や幕やのぼりがたち並び、関連公演であるこども寄席もしっかりPRされていて、ちょっと恥ずかしいくらいの気持ちになりました。正直めちゃめちゃ嬉しかったです。

場所は信毎メディアガーデン。こちらは今年の4月に完成したばかりの新しい建物で、建築設計は世界的な建築家・伊東豊雄氏によるもの。本当に素敵な建物で、中に入っているお店も素晴らしい~。地ビールとコーヒーは堪能しましたが、ジビエは食べられなかったです(心残り)。
こちらのコミュニティスペースを利用し、約240席近い席を作り、高座を組んで会場としました。この場所はまつもと市民芸術館の館長でもいらっしゃる串田和美さんがプロデュースされただけに様々な舞台・芸術が披露されることを前提に作られているだけに、本当に素晴らしい会場に早変わりしました。そこにお越し頂くのは、まさしく若手では最高の落語家と講談師、桂宮治さんと神田松之丞さん。さらに色物に江戸曲独楽の三増紋之助さんを迎えて、誰が見ても最高に楽しい、おもしろい落語会を提供させて頂きました。

一席目/神田松之丞 絵付き講談「違袖の音吉」
いつもは凄みのある親分役が板についている松之丞さんが、やんちゃな子どもを演じるのもまた見物でした。
色物/三増紋之助 江戸曲独楽
もう、この方のステージはあらゆる色物芸の中でも会場との一体感が半端ない。芸のレベルはもちろん、会場の熱気も半端なかったです。
二席目/桂宮治 お菊の皿
なんの落語も器用に、本当に面白くアレンジされる宮治節はこのお菊の皿でも健在でした。
おまけ/ジュニア大喜利
宮治さんの名司会っぷりに、ただ脱帽。笑点の次期司会、決定ですね。午前・午後ともに会場はほぼ満席で、たくさんの子どもたちの笑顔に出会うことができて、本当に幸せでした。
こども寄席は松本でも十分受け入れられそう。ぜひぜひこれからも伺わせてください!カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.06.04
6月3日 THEこども寄席初夏の宴 無事終了
6月3日(日)
THEこども寄席 初夏の宴
場所/深川江戸資料館小劇場
出演/林家彦いち、柳家花いち、おじゃるず梅雨の前の少し汗ばむ陽気の中、深川江戸資料館小劇場にて開催されました「初夏の宴」。午前・午後ともに200名以上のお客様にご来場頂くことができました。ありがとうございました。



【公演前イベント】はんこワークショップ
「夏のひととき」というテーマのもと、はんこアーティスト・アイダミツル作のオリジナルはんこを思い思いにポストハードに押すというワークショップを開催しました。どの子も自分の感性のままに、さまざまなハンコを自由に押して、何とも芸術的な一枚を生み出していました。ハンコというのは絵を描くのとはまた違い、とにかく気持ちに制約なく、計画もなく、好きに押すという感覚遊びのようなところが大きいのが、とても子どもたちに向いているようでした。出来上がったカードを並べてみると、甲乙つけがたい力作が並びましたが、彦いち賞、花いち賞、おじゃる賞を選んで頂き、表彰させて頂きました。
【落語一席目】柳家花いち 平林(午前)/寿限無(午後)
こんなに面白い若手落語家がいたんですね、と思った方が本当に多かったようです。優しいまなざしで子どもたちに語りかけ、所作の説明にはじまり笑いがはじける小話など、つかみはバッチリ。落語もわかりやすい演目を花いちさんならではのアレンジを加えてとても斬新。寿限無ってこんなに面白い噺でした?というお客様の声も聞かれたほど、子どもたちに大ウケの一席目となりました。

【色物】おじゃるず
この人たちの芸をなんと呼んでいいのかわかりませんが、とにかく面白いんです。トークしかり、太神楽をアレンジしたような曲芸しかり、お客様を巻き込んでのハラハラどきどきのショートステージも、すべておじゃるずエッセンスがたっぷりしみこんだオリジナルのコメディはとにかく愉快でした。コメディステージとして見ても楽しいし、色物曲芸としても見応え十分。おじゃるず、サイコーでした。

【落語二席目】林家彦いち 初天神(午前)/熱血怪談部(午後)
こども寄席で新作落語を披露した落語家さんはこちらの林家彦いち師匠で二人目。どうしても新作は子どもたちの反応は古典ほどよくない記憶が…と思いきや、彦いち師匠は違いました。初天神のウケもすごかったけれど、熱血怪談部は大爆笑の渦という感じ。彦いち師匠の第一印象を生かした熱血な先生役が子どもたちはもちろん、ママやパパにも大ウケ。彦いち師匠の熱の入った一席に、袖で見ていたスタッフも目が釘付けでした。公演終了後は、ハンコワークショップの表彰と、参加賞として好きなチュッパチャプス1本を贈呈しました。
子どもたちの笑顔いっぱいで無事終了となりました。※次回は9月2日の秋の宴となります。
先行予約は25日にご案内配信予定です。カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.04.24
THEこども寄席春の宴 in鎌倉 終了
THEこども寄席初となる、鎌倉芸術館での開催となりました。いつもよりもこじんまりとした会場で、落語家さんとの距離が近い、とっておきの落語会となりました。
4月21日(土)11時~、14時半~ 2回公演
場所/鎌倉芸術館 リハーサル室(100名)
出演/三遊亭萬橘、柳亭市童(落語)、のだゆき(ピアニカ他)<一席目/柳亭市童>

市童さんは本当に真面目で落ち着きのある落語家さん。ですが、高座に上がると人が変わったように、どこか渋みさえ感じさせる人情味あふれる落語を聞かせてくれます。今日は午前の部で「ろくろっ首」。ろくろっ首という言葉と首がのびるお化けのイメージはあるものの、その物語となると実際には聞いたことがない子どもがほとんどだったようでした。
<色物/のだゆき>

のだゆきさんの面白さはその巧みな演奏と、天然系を感じさせるゆったりと抜け感のあるトークです。そして一番最初のサプライズはリアル救急車の音。小学生なら誰でも持っているピアニカひとつでここまで再現できるという驚きのサウンドは何度聞いても感動するもの。さらには子どもたちが思わず口ずさんでしまう「さんぽ」の演奏もあり、子どもたちはもちろん、大人も大満足のひとときとなりました。
<二席目/三遊亭萬橘>

これほどライブ感を感じる落語は見られるものではないでしょう、というのが率直な感想。落語教室さながらに、座布団の正面はどこ?と解説をしてみせたかと思いきや、会場の子どもたちの反応に大いに突っ込みを入れ、その会場でしか味わえない笑いを生み出していけるのは、萬橘師匠だからなせる技です。さんざん子どもたちにいじり倒された後に披露した落語は「味噌豆」。味噌豆をほおばる仕草を見ているだけでお腹がすいてきたのは私だけではなかったはず。
カテゴリ:公演情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.02.20
みんなの落語会in湘南平塚 スペシャル開催


約1年ほど前よりららぽーと各店にて開催しております、鑑賞無料でどなたさまでも落語が楽しめる「みんなの落語会」。現在、ララガーデン春日部、ららぽーと海老名にて開催しておりましたこの落語会が、2月18日より8回連続スペシャルでららぽーと湘南平塚にて開催することになりました。
実はこちらの落語会をディレクションしておりますのが私ども。これまで10年の「THEこども寄席」を通して培った、大人から子どもまで楽しまさせて下さる落語家さんとのつながりを生かしてさらに多くの方に落語を楽しんでいただくべく、尽力しております。今回のトップバッターは立川晴の輔さん。テレビ神奈川で「キンシオ」という人気番組にレギュラー出演されていることもあり、初回から満席の大賑わい。やはり満席となると噺家さんの心持ちもぐぐっとよくなり、いつも以上に気合いの入った一席を披露くださいました。
さらに3月11日(日)はスペシャルのスペシャル版として林家彦いち師匠が登場。これで無料とは、本当に美味しい限りです。
ちなみに、今回ポスター画を手がけていただいたのはチャンキー松本画伯。すべての落語家を有名浮世絵の一枚に仕立て直しいただき、イラスト化しました。これには、落語家さん皆さんも感動されていて、大いに盛り上がりました。これからも「みんなの落語会」ぜひご注目ください。
カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.02.18
THEこども寄席2018 新春特別公演 無事終了
2月17日(土)
日本橋公会堂にて開催しました「THEこども寄席2018新春特別公演」。
午前の部、午後の部ともに、満席に近いお客様を迎えることができました。心より御礼申し上げます。【公演前イベント】ミニ縁日



射的やピースガン、福笑い、投扇興に独楽回し。小さなブースながらも5~6種類の昔遊びを用意して公演前の1時間、存分に遊んでいただきました。ただ、今回100名以上の子どもたちを迎えるのは初の試みだっただけに、思いがけず大混雑となったブースも多々あり、お客様にはご迷惑をおかけする一面もありました。(猛反省しております)それでも多くの子どもたちがいろいろな表情を見せて真剣に取り組んでくれていたのが印象的でした。やはり一番人気は射的!来年は列を増やします!
【一席目/春風亭昇々】

ポンキッキーズ(2018年3月番組終了)の司会もなさっていたこともあり、子どもたち相手はお手の物、という昇々さん。小話でも、落語でも、子どもたちが喜びそうな部分をオーバーリアクションで演じ、笑いを増幅させているのはさすが。加えて表情豊かなその落語スタイルは、はじめて落語を聞く子どもたちにもインパクト十分でした。
【色物/セ三味ストリート】

こども寄席で「三味線」というのはありそうでなかった出し物。子どもたちに三味線の面白さはまだ難しいのでは?という心配は全く無用でした。セ三味ストリートのお二人の三味線はその音楽のみならず、パフォーマンスの素晴らしさにあるため、子どもたちも大人も大興奮。アンケートでも「あんなに面白い三味線を聞いたのは初めてで感動しました」という声を数多くいただきました。
【二席目/桂文治】

よく通る声で、あかるい表情で、誰にでもわかりやすい落語を披露くださった文治師匠。親子向けの定番の演目「牛ほめ」も文治師匠がやると、どうしてこうも面白くなるものか、本当に不思議なものです。子どもたちにも十分そのおもしろさは伝わっていたようです。普段はほとんどされない、落語のいろは(道具の説明や所作の解説など)も指南いただいて、貴重な一席となりました。
カテゴリ:公演情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye -
2018.01.08
2018年1月7日 いろは寄席

2018年の幕開け落語会は「いろは寄席」でした。
こちらの公演は二子玉のコミュニティクラブたまがわが主催する
親子向けの落語会で、私どもが全面サポートしております。100名弱のこじんまりとしたスペースで、子どもたちは前のマットに
座って、間近で落語をご覧頂き、さらには公演途中でちょっとした
落語体験もあったり、落語家と一緒に写真撮影ができたりと、
ただ聞くだけではない、ふれあいがいっぱいの落語会となっております。初回の出演は三笑亭夢丸師匠。夢丸師匠の笑いがたえない落語解説は
子どもたちに大好評。落語はもちろん、小話も連発で
子どもたちの笑い声が絶えない1時間となりました。次回は5月6日(日)の開催予定。出演は鈴々舎馬るこ師匠です。
今度はどんな落語会となるのか楽しみです。
(いろは寄席のご予約は1ヶ月前よりコミュニティクラブたまがわのホームページにて受付予定です)カテゴリ:出演者情報comments(0) | Trackbacks (0) | by childeye
Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/childeye/kodomoyose.jp/public_html/wp-content/themes/kodomoyose2024/archive.php on line 27
Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/childeye/kodomoyose.jp/public_html/wp-content/themes/kodomoyose2024/archive.php on line 27